連載第9回 パリ・ムウドンの丘 3
新連載・石田郁代著
ロダン夫婦の思ひ出
文/写真 石田郁代

西暦2000年のブレード・エッフェル塔
詩、ロダン夫人の賜へる花束
与謝野晶子 初出大正5.7 文章世界
とある一つの抽斗(ひきだし)を開きて、
旅の記念の繪葉書をまさぐれば、
その下より巴里の新聞に包みたる
色褪せし花束は現れぬ。
おおロダン先生の庭の薔薇のいろいろ……
我等二人はその日を如何で忘れん、
白髪まじれる金髪の老貴女、
濶(ひろ)き梔花色(くちなしいろ)の上衣を被(はお)りたる、
けだかくも優しきロダン夫人は、
みづから庭に下りて、
露おく中に摘みたまひ、
我をかき抱きつつ是れを取らせ給ひき。
花束よ、尊く、なつかしき花束よ、
其日の幸ひは猶我等が心に新しきを、
わづかに三年の時は
無残にも、汝(そなた)を
埃及(エジプト)のミイラに巻ける
五千年前の朽ちし布の
すさまじき茶褐色に等しからしむ。
われは良人(おっと)を呼びて、
曾(かつ)て其日の歸路、
夫人が我等を載せて送らせ給ひし
ロダン先生の馬車の上にて、
今一人の友と三人(みたり)
感激の中に嗅ぎ合ひし如く、
額(ぬか)を寄せて嗅がんとすれば、
花は臨終の人の嘆く如く、
つと仄かなる香を立てながら、
二人の手の上に
さながら焦げたる紙の如く、
あはれ、悲し、
ほろほろと碎け散りぬ。
おお、われは斯(か)かる時、
必ず冷やかにあり難し、
我等が歡樂も今は
此花と共に空しやなるらん。
許したまへ、
涙を拭ふを。
良人は云ひぬ、
「わが庭の薔薇の下(もと)に
この花の灰を撒(ま)けよ、
日本の土が
是に由りて浄(しづ)まるは
印度(いんど)の古き佛の牙を
教徒のもたらせるに勝(まさ)らん。」

『定本与謝野晶子全集』第十巻(316頁~319頁)より
5年前(明治45年6月)ロダン夫人が、自ら摘んで晶子に捧げた花束を、彼女は大切に日本へ持ち帰ったのだろう・・・。ドライフラワーの薔薇は、パリのムウドンの丘を思い出させ、6月のあの日のロダンとの会見を思い出させた。
浪漫派歌人・晶子は何歳になってもロマンチックな、夢を追いかける歌人であった。
詩・蟲干の日に
与謝野晶子 初出大9.8 婦人の友
蟲干の日に現れたる
女の帽のかずかず、
欧羅巴(ヨーロッパ)の旅にて
わが被(き)たりしもの。
おお、一千九百十二年の
巴里(パリ)の流行(モード)。
リボンと、花と、
羽飾りとは褪せたけれど、
思出は古酒の如く甘し。
埃(ほこり)と黴(かび)を透(すか)して
是等(これら)の帽の上に
セエヌの水の匂ひ、
サン・クルウの森の雫、
ハイド・パアクの霧、
ミュンヘンの霜、維納(ウイン)の雨、
アムステルダムの入日の色、
さては、また、
パガテルの薔薇の香(か)、
佛蘭西(フランス)座の人いきれ、
猶残れるや、残らぬや、
思出は古酒の如く甘し。
アウギュスト・ロダンは
この帽の下にて
我手に口づけ、
ラバン・アジルに集る
新しき詩人と畫家の群は
この帽を被たる我を
中央に裾(す)ゑて歌ひき。
別れの握手の後(のち)、
猶一たびこの帽を擡(もた)げて、
優雅なる詩人レニェの姿を
我こそ振返りしか。
ああ、すべて十とせの前、
思出は古酒の如く甘し。
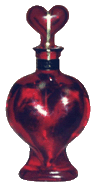
『定本与謝野晶子全集』第十巻(316頁~319頁)より

昭和2年春-文化学院にて- (『定本与謝野晶子全集』第十三巻より転載)
西欧より帰国後、晶子の肖像の特徴は、帽子をかぶった写真が多い。上記の詩は、前詩より4年後の作品である。パリより帰国して9年の歳月が流れても、ロダンとの出会いが彼女の心の裡を独占し、忘れられなかったのだろう。
帰国後に誕生した我が子にロダンの洗礼名(アウギュスト)を、命名したことでもうかがえる。
とまれ上記西欧より帰国後、2編の詩は、どんな説明も不要い思い出がうたわれている。
人は皆、旅の印象は何時までも忘れない。まして、今から90年前、日本女性が海外旅行するなど夢のような時代(明治45年)に、愛する夫と共に遊んだヨーロッパ旅行の思い出は、晶子の心を深くとらえて離さなかったのだろう。

セーヌ川舟遊(2000.7.5) -むかしも今もかわらない-
1912年6月18日の午後、ロダン夫人の厚意で、馬車でセーヌ川の船着場まで3人は送って貰った。船でセーヌ川をさかのぼり、アレキサンドル三世橋で下船、自動車でロダンのアトリエ、オテル・ビロン翁を訪ねた。
ロダン翁は快く3人を書斎に招じ入れた。テーブルの中央にロダン翁が座わり、その両隣に先客の候爵夫人と晶子。夫人の隣に寛、松岡氏が座った。この座席はロダン翁が決めた。
ロダンは<背のやや低い、腹の出た太い大きいロダン翁は皆に握手をした>と、晶子は記している。<ロダンは銀髪で、ねずみ色のアルパカの上衣に黒いズボンをはき、鼻眼鏡をかけ大きな椅子に座り、70歳とは見えないほど血色のよい頬をしていた。そして、たえず太洋のうねりのような大きい微笑を浮かべて会話をした>20世紀初頭の話題の芸術家ロダンと、明治の女性(33歳)歌人が対面した。
残念なことに、晶子はフランス語が喋れなかった。<私は唯だ痴鈍な微笑の下に頭(うなづ)いて居ました。私は翁に向いて何を問うてよいか何を語ってよいか全く考へ附きませなんだ>(略)(『ロダン翁に逢った日』339頁)
まのあたりロダンを見たる喜びを
云はんとすれば唖に似るわれ
晶子
晶子注解「短歌の鑑賞と作り方」より
(前略)先生の芸術は余りに偉大である。わたしは余りに小さな人間である。そうして、此の幸ひは余りに大きい。ああ、わたしは何もえひ得ない。何と云ふべきかを知らない。先生の前に於けるわたしは唖にひとしい、と嘆いたのである。
『定本与謝野晶子全集』第十三巻(413頁)
晶子ほどの才媛が、フランス語の出来ない事を恥づる事なく正直に書いている。歌壇の女王の、このような純粋さに私は頭が下がる。また、普段から彼女は、しゃべる事は苦手な人だった。

ビロン館のアトリエでのロダン (このビロン館で夫婦らがロダンと出会った。現在 ビロン館は、ロダン美術館となっている。)
アトリエでのロダンとの歓談は夕暮れまで続いた。 ロダンは記念に、自分の写真に署名をして晶子に渡した。(HP、拙稿第3回の詩を参照)
玄関まで送り出たロダンは、晶子の右の手を取り、西洋式の別れの接吻をした。 憧れの世界の巨匠オーギュスト・ロダン翁より突然、自分の手に接吻された晶子の高揚ぶりが、90年後の今、目に彷彿とする。
晶子はその秋(大正元年)、ひとりで帰国。(マルセーユ港より出港した)寛は翌年(大正2年)1月に帰国した。
大正6年、ロダンもロダン夫人も逝去したが、晶子の心に残る思い出は、10年を経てもなお、昨日のように鮮烈であったことが、冒頭2篇の詩に如実に表現されている。

左・往時のビロン館 全景/右・現在のロダン美術館入口
思出の中にたふとく金色すロダン
と在りしアトリエの秋
晶子

与謝野晶子百首かるた





