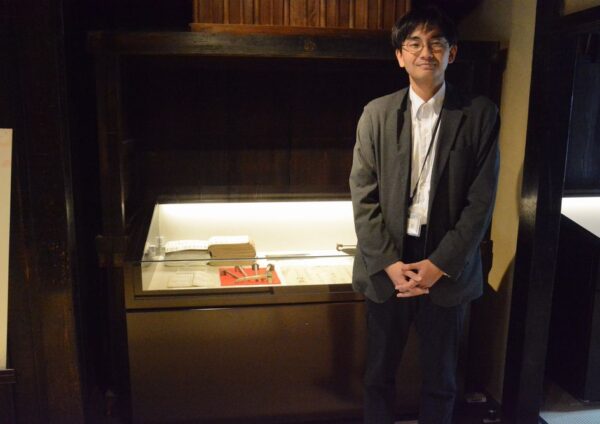企画展『ミュシャとアメリカ』レビュー(2)
『ベル・エポック(良き時代)』と後に言われる事になる華やかなイメージのある時代。19世紀最後の年、1900年にパリ万国博覧会は開催されました。文明の発展と膨張する帝国主義が重なりあう時代の、この万国博覧会は、アルフォンス・ミュシャの人生にとって大きな転機となるものでした。
堺アルフォンス・ミュシャ館で開催されている企画展「ミュシャとアメリカ」(1)。その第2章は「1900年のパリ万国博覧会」です。案内は前章に引き続き学芸員の川口裕加子さんです。
■“スラヴ民族”に目覚める
パリ万国博覧会が開催された1900年には、すでにアルフォンス・ミュシャは、デザイナーとしては売れっ子で、多忙の日々を過ごしていました。「ポスターや舞台装置の装飾パネルのといった商業デザインの仕事」に忙殺されていたそうです。
――これまでは一般的にイメージされる「デザイナーとしてのミュシャ」でしたが、一体何があったのでしょうか?
川口「この時期のミュシャは、パリのデザイナーとして成功していた時期で、商業ポスターやリトグラフの作品が多かったのですが、パリ万国博覧会前後からは油彩画を描きはじめます」
--当時は、油彩で歴史画や神話画を描いてこそ、正統な画家と評価されるとおっしゃってましたね。方向転換のきっかけはなんだったのでしょうか?
川口「大阪で行われた万国博覧会もそうでしたが、各国のパビリオンがありますよね。ある国がミュシャに博覧会のための仕事を依頼してきたのです。それがミュシャにとってのきっかけとなったのです」
ミュシャのもとに舞い込んだのは、パリ万国博覧会のボスニア・ヘルツェゴビナ館の壁画制作の仕事でした。前章でも取り上げたように、ミュシャはもともと歴史画家を目指して故郷のチェコからパリへと留学しました。どれほどデザイナーとして成功しようが、初志は歴史画家です。きっと願っても無い仕事だったに違いありません。
そしてもう1つこの仕事を人生の転機にした重要な要素はボスニア・ヘルツェゴビナでした。ボスニア・ヘルツェゴビナに暮らしている人々は、チェコと同じスラヴ民族であり、チェコもボスニア・ヘルツェゴビナもオーストリア=ハンガリー帝国の施政下で苦渋を舐めていたのです。
――スラブ民族というと、とりわけ苦難の歴史を歩んできた民族という印象がありますね。アジアとヨーロッパの間の民族が行き交う十字路地域にいて、ビザンティン帝国やオスマン帝国の支配下にあって……。ミュシャの時代はオーストリア帝国ですか?
川口「正確に言えばミュシャが生まれた頃はオーストリア帝国で、その後1867年からオーストリア=ハンガリー帝国になっていますね」
――チェコは、オーストリア帝国の前は、神聖ローマ帝国の支配下。ボスニア・ヘルツェゴビナだと、オスマン帝国統治時代があって、その後オーストリア=ハンガリー帝国に組み込まれたのですね。
川口「ミュシャは、ボスニア・ヘルツェゴビナ館の壁画制作のために、ボスニア・ヘルツェゴビナへ取材旅行に出かけました。そこで祖国チェコと同じようにオーストリアの施政下にあるスラヴ人と出会い衝撃を受けたようです。ミュシャは地域を越えたスラヴ民族の連帯が必要だと感じるようになり、《スラヴ叙事詩》を構想しはじめたのです」
――ミュシャの中のスラヴ民族としての目覚めが、歴史画家への一歩を踏み出させたということなんですね。
■《スラヴ叙事詩》が描いたもの
後にミュシャの生涯をかけての大作となる《スラヴ叙事詩》は、古代から現代にかけてのスラヴ民族の歴史的場面を描いた全20作の連作です。2017年、日本で開催された『ミュシャ展』ではじめて全20作がチェコ国外で展示されることとなり、大きな話題となりました。日本のミュシャブームが再燃するきっかけとなったのは、この『ミュシャ展』であり、《スラヴ叙事詩》といえるかもしれません。
《スラヴ叙事詩》は、一枚一枚が何メートルもの巨大な絵ですが、企画展『ミュシャとアメリカ』ではそのミニミニサイズのパネルと解説が展示されていました。
このパネル展示では、最初の6作を「古代の繁栄と苦難」、第7作~16作までを、「中世のフス戦争」「弾圧と流浪」、17作~19作を「支配からの解放」とテーマごとに分けて解説しています。スラヴ民族が、古代から現在に至るまで、受けてきた苦難、なしえた繁栄はかくの如しだったと見せつけられます。
そして20作目を「スラヴ民族の賛歌」には、4つの時代が青(古代)・赤(中世)・黒(かつての敵)・黄色(独立の喜び)で織込まれており、長い歴史のうねりが凝縮しスラヴ民族の未来を讃える一枚へと昇華されています。
ミュシャの幻想的な筆致で描かれた作品を観ることでスラヴの人々は、スラヴ民族であることの苦さと誇りを噛みしめることとなるでしょう。
こうしてみると、故郷のチェコの歴史だけでなく、スラヴ民族全体の歴史を描いた所に、ミュシャのユニークさがうかがえます。単純な愛国者というわけでもなく、情熱と同時に幅広い視点、歴史観の持ち主でもあったのでしょう。
そしてこの作品の出発点になったのが、1900年パリ万国博覧会。時計の針を巻き戻してみることにしましょう。
■1900年パリ万国博覧会
川口「第2章『1900年パリ万国博覧会』では、この時期にミュシャが手がけた作品を展示しています」
――このコーナーで雰囲気が変りますね。インパクトのある油彩画の大作が目に飛び込んできます。これは《クォ・ヴァディス》ですね。そういえば、ミュシャは信仰はあったんですよね? チェコは正教ですか? カソリックですか?
川口「ミュシャはカソリックで洗礼を受けました。1899年にはキリスト教の祈祷文をイメージとして表した『主の祈り』を自主的に作成しています。それも祈りの言葉を装飾的に描き、イメージ画も添えるという力の入れようです」
――頼まれたわけじゃなくて、自主的にっていうのがすごいというか、ミュシャらしいですね。
川口「この《クォ・ヴァディス》はアメリカにも持って行っています」
――アメリカに名刺代わりにつきつける作品だったんですね。しかし、堺アルフォンス・ミュシャ館のコレクションはすごいですね。どの作品がコレクションの中で一番代表作といえるのでしょうか? ちょっと下世話な話ですが、値段的に並べると……とかはできるものなのでしょうか?
川口「それはなんともいえないですね。代表するとなると……どの作品も素晴らしいですが、この《クォ・ヴァディス》や、サラがミュシャのデザインから作らせた《蛇のブレスレット》、《ウミロフ・ミラー》もありますし、《ハーモニー》も……」
――《ウミロフ・ミラー》もこのコーナーに展示されてますけど、やはりいいですね。貴族のお家に飾られていたんでしたっけ?
川口「ミュシャの友人でオペラ歌手のチェコ人ボザ・ウミロフの自宅のマントルピースを飾っていました。《ウミロフ・ミラー》は、ミュシャが渡米した1903年から1904年にかけて制作されています。音楽家の家の作品ということで、モチーフには歌や音楽と関連するものが多くみられます。背景には巨大な人物が見えるのですが、この何かの象徴と思しきこのモチーフは、《ハーモニー》にも類似しています」
――《ハーモニー》は、さらに《スラヴ叙事詩》を思わせますね。
川口「このコーナーの最後は、ボスニア・ヘルツェゴビナ館の壁画の下絵(※トップ画像)になります。さすがに、壁画の本物はないのですが」
――この下絵を見ても、群像で歴史のワンシーンを描いているところは、《スラヴ叙事詩》へと繋がっていくのかな? と思わせますね。デザイナー時代の後、歴史画家として歩み始めたパリ万国博覧会時期のミュシャから、後の萌芽が見えてくるようで面白いですね。
しかし、ミュシャが実際に《スラヴ叙事詩》を書き始めたのは10年後の1910年。それから16年もかけて《スラヴ叙事詩》は描かれることになります。これほどの情熱を込めた大作を描くために、ミュシャはアメリカへ行かねばなりませんでした。
さて次回は、いよいよアメリカ時代のミュシャについてです。
企画展『ミュシャとアメリカ』
会期:開催中→2021年3月21日(日)まで
会場:堺アルフォンス・ミュシャ館
開館時間:午前9時30分から午後5時15分(入館は午後4時30分まで)
休館日:月曜日(休日の場合は開館)、休日の翌日(2月12日、2月24日)
観覧料:一般510円(410円)、高校・大学生310円(250円)、小・中学生100円(80円)
*( )は20人以上100人未満の団体料金