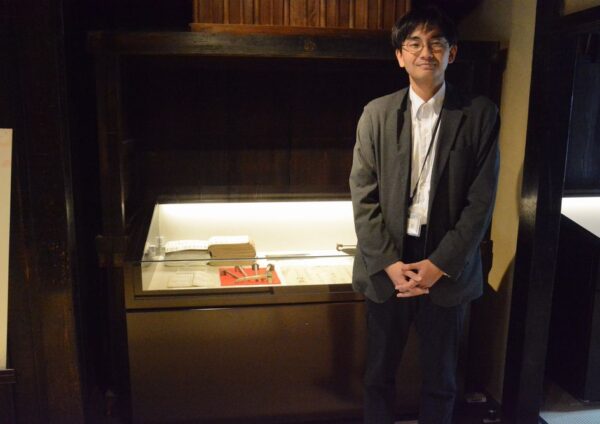劇場から世界を変える!! アジアンユースシアターフェスティバル(4)
「お手本になるべき大人が、笑顔も見せずに何をしているのか」
アジアの12カ国14団体が参加したアジアンユースシアターフェスティバルの運営スタッフから、筆者は名指しで注意を受けました。まったくもってその通りなので、ぐうの音も出ません(第3回記事)。
自分のカメラでこのフェスティバルにどんな貢献が出来るのか。「自分に何が出来るのか、考えなさい」という言葉が突き刺さります。幸いお手本がいました。ベトナムのカメラマントゥルン(Trun)さんです。英語なんてほとんど話せないのに、笑顔で人の輪に入っていって素晴らしい写真を撮る彼。
日本から来たもう1人の撮影スタッフのヨッシーさんと共に汚名返上の最終日が始まりました。
■使命を果たそう
「子どもたちの笑顔を通じて、フェスティバルの素晴らしさを伝えよう」
筆者とヨッシーさん。2人の日本チームの撮影スタッフは、手分けして撮影にあたることにしました。ヨッシーさんが、フィリピンチームのワークショップに向かっている間、筆者は残った子どもたちがはじめたゲームの様子を撮ることにしました。なんのゲームか良くわからなかったのですが、なんと日本でも大流行した“人狼ゲーム”でした(村人の中に紛れ込んでいる狼男が誰かをあてるゲーム)。
ゲームの輪から次第に参加者が排除されていくゲームなので、この隙に暇になってしまった子どもたちに話しかけて写真を撮るようにしてみました。ファインダーを覗くと、子どもたちがフェスティバルから支給されたお揃いのカラーTシャツをすでに着ていないことに気づきます。一体感を出していたTシャツでしたが、この3日間の間に子どもたちはすっかり顔見知りになっており、もう必要が無くなっていたのです。
「写真を撮っていい?」
と言葉をかけると、みんな笑顔になります。仲良くなった他のチームの誰かと写真を撮って欲しい。そんなリクエストにも応えていきます。
少しはフェスティバルに貢献できているだろうか。そんな事を思っていると、ふと気になる集団がいることに気づきました。同じチームで固まっていて、ゲームの輪に加わろうとしていない様子です。
「写真撮ってもいいかな?」
と声をかけると、はにかんだような笑顔を浮かべます。彼らはベトナムチームでした。
「ベトナムの作品を見ました。あなたがデザイナーですね。伝統的な美意識と現代的なセンスが融合しているように感じました。日本のサブカルチャーの影響もあるのでしょうか?」
「ありますね!」
「日本のアニメや漫画は好き?」
「好きですよ」
そんな所から話が盛り上がりました。どうもベトナム人も日本人のようにシャイな所があるようですが、話しかけるとフレンドリーです。そういえば、日本人とベトナム人の遺伝的なルーツは近いという話がありますが、このシャイさも共通なのでしょうか??
ベトナムチームと同じテーブルで話し込んでいるうちに、いつの間にか時間が経ち、この日最初の公演の時間になりました。慌てて劇場へと向かいます。
■最終日の公演
演劇づけだった日々も今日まで。この日行われた3公演を紹介しましょう。
-
「BUMI」SEEDS THEATRE(ブルネイ)
「マザー・オブ・ネイチャー(自然の母)」など、自然の精霊たちと、本来なら接触できない人間界の若者が交流するストーリー。プラスチック製品のために、マザー・オブ・ネイチャーは体調を崩して起き上がれなくなってしまいます。その製品を作っていたのは若者の友人のアーティストだったというお話。異世界交流ラブロマンス風味でもありました。
-
「MANA RUMAH?」WORK IN PROGRESS(マレーシア)
労働階級の分断によって社会に貧困が生まれるといった社会構造の問題が語られていたように思います。体操選手のような高い身体能力を見せつけるダンサー達がいじめ、いじめられる若者たちを演じていました。彼らをバカにする男は、後にホームレスに。そして物語を外から俯瞰するストーリーテラーの役割を持つ2人の男女。もう1人、横笛を吹く音楽家のような人物が出てきますが、物語の外と内をつなぐ天使かキリストのような人物かもしれません。
-
「TIIN TIIN……GOOD BYE FOREST & NEW WORLD」KHMER ART ACTION(カンボジア)
森林破壊がテーマで、トゥルントゥルンという若い木と年老いた木、それにナレーターが登場します。森林が伐採されて仲間の木がいなくなっていくことを、トゥルントゥルンは新しい世界に行けるのだと喜びます。しかしそんなことはなかったわけです。
これによって、全団体の公演が終わりました。
が、実はシークレット企画が、もう1つあったのです。
■シークレット企画 クロージング公演
シークレット企画は、各団体から1名ずつ選ばれて、14名の若者が4日間で1つの作品を作り上げて、閉会式で発表するというものでした。監督は、フィリピン、バングラデシュ、そして日本から3名選ばれました。日本の監督は、アドバイザーとしてチームを率いていたTheatre Group Gumboの代表田村佳代さんでした。当初は、3人の監督が4~5人ずつの若者を担当し10分程度の作品を作るような予定だったそうですが、バングラデシュの監督が田村さんとの実力差を認め「自分は勉強させてほしい」と自ら認めてアシスタントとなり、結局前半部を田村さんが1人で監督し、後半を3人の監督が共同で監督することになったのだそうです。
作品制作は、参加したメンバーがそれぞれ社会に対して思っていることや、舞台でどんなことをしたいのかなどを話し合うところからはじめたのだそうです。英語が得意な子ばかりではなかったので、絵を描いたりして意思疎通したのだとか。子どもといっても、10才ぐらいから20代後半までいるし、受けてきた芸術教育もバラバラでした。
「日本とシンガポールは先進国でしたが、よく似ていました。技術的には上手いんだけれど、自分の意見を言わない。指示待ちになってしまう。ベトナムの子は14才だけど、すごい意見も言うし、周囲をコントロールしようとする。そんなことをしなくていいというと、自分の役割をすぐに理解して、バランスを取るようになった。頭のいい子だったけれど、技術があるわけではなかった」
個性豊かな14人の子どもたちに演出をつけていくのは大変な作業だったそうです。
閉会式でのショーは、見事なものでした。
14人の個性が1人1人活かされ、無言劇なのに何が語られているのかが良くわかり、かつユーモアがそこかしこにちりばめられていて客席から笑いが生まれます。役者の個性を利用しながら、深いテーマを喜劇で語ることを得意とする田村さんの面目躍如という所でしょうか。バングラデシュの監督が素直にシャッポを脱いだのも当然なことかもしれません。
強い目の光りが客席を射貫き、子どもたちが光の中まっすぐに歩く演出には鳥肌が立ちました。彼らを待ち受ける困難な未来。でも、彼らは未来を信じ歩んでいく。このフェスティバルを象徴するようなワンシーンでした。
ショーの後は、フェスティバルの開催に尽力したマレーシアの住宅・地方自治大臣のZuraida Kamaruddinさん、そして14人の若者がスピーチをしました。
あっさりと終わったかに見えた閉会式でしたが、その後はディスコタイムに。舞台の上では、踊りの輪が出来、すっかり打ち解けた子どもたちが、あちらで記念撮影、こちらで記念撮影をしています。ふと見ると、客席にはベトナムチームのメンバーがいました。ちょっと他のチームと様子が違ったのは、全員が一分の隙も無い豪華な礼服を着こなしていることでした。閉会式だから厳しいドレスコードで挑んだのでしょう。ベトナムチームの生真面目な個性がこんなところでも出ていました。
午前中にテーブルを囲んだこともあって、ベトナムチームは嬉しそうに話しかけてきました。目配せすると、全員が声を合わせて、
「ありがとうございました」
と、日本語で挨拶してくれたではありませんか。これには本当に驚きました。カメラを手に走り回って良かったと心の底から思った瞬間でした。
こうした国境を越えた交流は、このフェスティバルのそこかしこで起こっていることでした。閉会式を見渡せば、あちこちで記念撮影やハグが交わされています。もはや、「国境を越えた」と形容すること自体が無意味で、無用の形容のように思えます。誰がどの国から来た子どもであるとか、そんなことはこの場では些細すぎてかすんでしまいます。そんなことはいつのまにか意識の外。それよりも、彼らがどんな演技をするどんなアーティストだったとか、ワークショップや普段どんな様子で、どんな個性でどんな会話をかわしたとか、そんなことの方がはるかに鮮明な記憶として残っています。
こうしてフェスティバルは全日程を終えました。次の日はオフで、深夜便で帰国する予定だったのですが、話はそれで済まなかったのです。
(第5回に続く)
●関連情報
アジアンユースシアターフェスティバル2020の情報はこちら→web
アジアンユースシアターフェスティバル日本チームの情報はこちら→FaceBook